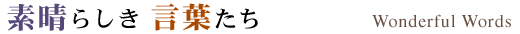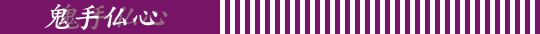天台宗全国一斉托鉢始まる
- 心の田を耕す -
 今年も、寒風の中を天台宗の全国一斉托鉢が始まった。
今年も、寒風の中を天台宗の全国一斉托鉢が始まった。托鉢は、行乞(ぎょうこつ)ともいわれる。
インドでは出家した男性を比丘、女性を比丘尼というが、その意味は「乞(こ)う人」で布施によって生活する人のことである。
釈尊が、マガダ国で、田を耕していたバラモンに食を乞われると「人に頼らずに、自分で田を耕して食え」と罵倒された。その時に釈尊は「我もまた田を耕すものなり」と言われたのである。それは、心の田を耕すという意味であった。
「信仰が種子である。苦行が雨である。智恵が農具である。恥ずかしいと思う気持ちが鋤棒である。そして人々の心を耕し、あらゆる苦悩からの解放という実をみのらせるのだ」。
この中で釈尊は、また「体をつつしみ、言葉をつつしみ、過食をしない」とも言われ、托鉢とは単に食を得る行為ではなく「少欲知足」を実践し、人々に布施をさせる尊い行為であると語られた。今も、仏教国のタイやラオスでは、喜捨する人々の方がへりくだっている光景が見られる。
今、天台宗が展開している全国一斉托鉢は、国内外の弱者救済のために行うものだ。僧が自らの食を乞うという形からは少し離れる。しかし、釈尊が説かれた心の田を耕すという意味では、なんら変わりがない。
それは、あなたの心にある仏心を耕すことであり、また私の仏心を耕すことである。
執着を捨て、他者の幸せを祈るみ仏のこころに添うよう努めてゆきたい。
毎年、決まった場所で待っていてくれる方がいる。恥ずかしそうにして募金箱にいれてくれた少女がいる。お米を下さる方がいる。多額の浄財を下さった老夫婦もいる。
その暖かいこころに、私たちのこころを添えて、待っている人々に届けたい。
人々のために托鉢をすることによって、我もまた田を耕すものでありたいと思う。